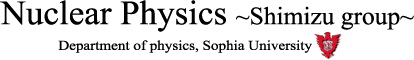
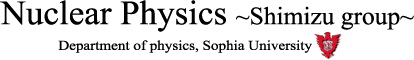

原子核を構成する陽子と中性子(総称して核子)は現在ではクォークからできていると考えられています。クォークの場を記述する理論は、グルオンをゲージ粒子とする、非局所ゲージ理論で、量子色力学(QCD=Quantum Chromodynamics)です。クォークの質量は3〜7MeVと考えられており(陽子は939MeV)非常に小さく、ゼロの場合に成り立つカイラル対称性(Chiral Symmetry)が重要な役割を果たします。そして通常の世界ではこの対称性が自発的に破れていて、クォークはおよそ300MeVの質量をもつ構成クォークとして振る舞い、破れに伴って現れる擬スカラー中間子や、グルオンを媒介とした相互作用を行います。
現在研究室で中心的に行っている研究テーマは、核子やそれに類似したハドロンと呼ばれる粒子をクォークの3体系として取り扱う模型を使った、ハドロンの種々の性質の研究です。核子の大きさがおよそ1fmで、その中に質量が300MeVの粒子が運動しているとすると、当然相対論的な取り扱いが必要になります。そのために厳密な取り扱いは非常に困難になるので、いくつかの近似を用いてハドロンの性質を記述することを試みています。主な方法として、相対論的な波動方程式(ディラック方程式)から出発して平均場近似を用いる方法と、非相対論的な記述の枠組み内で相対論的な効果を補正項として考慮していく準相対論的な方法です。
またこれらの研究と平行して、クォーク模型を使って、核子同士の相互作用を研究することも重要なテーマです。核子間の相互作用は、散乱の実験から近距離で強い斥力があると考えられていますが、これを核子がクォークからできている複合粒子として取り扱うことで説明しようとする試みが世界中で行われています。この分野の研究も簡単化された非相対論的模型で積極的に進めていますが、より洗練された核子の模型、特に相対論的な効果を考慮できる模型と整合性のよい核子間相互作用の記述を目指して研究しています。
具体的な研究は、昔の理論物理学のイメージとは異なり、計算機を使った数値計算が主流です。ただし得られた結果をもとに、何が本質的なのかを判断したり、議論することは数値計算よりもずっと興味あることで、大学院生や共同研究者と楽しく議論しながら研究を行っています。

2001年度 卒業研究生・・・池田俊介、大橋義裕、田房誠一郎、滝澤直也
2002年度 卒業研究生・・・江守昭憲、小林直紀、森野英哲、西納大介、野村詩穂